👩👧👦 1. 出産や子育て、専業主婦に対し社会が正当に評価する「価値観」を取り戻す
国家は国民なしには成立せず、日本人の「子ども」は「未来の日本」そのものです。国家にとって、出産や子育ては国の根幹となる営みの一つであり、特に出産を担う女性を尊重しなければなりません。
これまで国が積極的に進めてきた女性の社会進出が一般化する中で、「職業人としての女性」だけではなく、「専業主婦」も女性の尊い選択肢であり、「将来の夢はお母さん」という価値観を取り戻す必要があります。

主な施策
- 社会進出一辺倒ではなく、お母さんや専業主婦は女性に与えられた大切な選択肢であることの理解を推進する(女性活躍推進法に専業主婦支援を追加)。
- 女性の重要なキャリア分岐点においても、妊娠・出産と年齢や生活習慣の影響など科学的に正しい情報をもとに、社会進出志向のみに偏らない判断ができる環境づくり。
- キャリアや経済的安定を待つうちに、結婚や出産が遅くなり、子どもが欲しくても授からないケースを減らすため、将来の希望と安定を感じられる社会づくり。
💼 2. 一馬力でしっかり稼げて、女性が望めば安心して家庭に専念できる「経済」支援
小泉政権時の非正規雇用推進以降、非正規雇用の増加とともに未婚率が増加の一途をたどり、少子化の大きな要因となっています。
また結婚後も、男性の非正規雇用の増加などによる家計の手取り減少で共働き世帯が急増し、妊娠出産を担う女性の一部は不本意に働かざるを得ない状況が出産や子育ての障害となり、少子化に拍車をかけています。
政府は「異次元の少子化対策」として年3.6兆円の支出を行ってきましたが、改善の兆しは見えず、さらに大胆な財政出動が必要です。
主な施策
- 派遣業務範囲の見直しなど、労働者派遣法改正による非正規雇用の正規雇用化。
- 正社員雇用より派遣社員活用の方が企業会計上有利にならないよう税制改正。
- 不妊治療費の助成事業を強化。
- 子育て教育給付金の定額給付(子ども一人につき10万円/月)及び、出産費用や子育てに必要な住居・車など取得時の随時給付。
- 第一子より段階的に減税し、人口増に寄与する第三子より非課税世帯化(子育て減税)。
- 第二子以降の返済猶予や元本帳消しにより、多子世帯では実質無償になるローン創設(子育てローン)。
- 子どもの数に応じて年金を加算(子育て褒賞年金)。

🏘️ 3. 夫婦のみならず、家族や地域で育て、出産育児が女性のキャリアの価値になる「制度」支援
現在の日本の家族形態では、多くの家庭で出産や子育ての負担が核家族の夫婦に集中しています。
また働き続けたい女性のキャリアと出産子育てとの葛藤が女性に負担を強いています。
夫の育児参加の推進に加え、旧来の日本に見られた多世代を含む「家族」や「地域」という共同体で子育て家族を支えられる制度を強化する必要があります。
主な施策
- 3年間はしっかり育児に専念すること(長期育児休業)を奨励し、補正した女性就業率を再評価する(育児休業中の人は非就業としてカウント等、M字カーブの推奨・再定義)。
- 育児や育児に関連した地域社会への関与は越境学習的要素があり、育児支援経験をキャリア形成上の価値や副業として企業が認めるようガイドライン化。
- 多世代同居・近居・共生や地域の助け合い環境をつくり、子育て負担を軽減し高齢者の活躍機会を増やす。
- 親族による家庭支援にあたっては祖父母等に対する育児休暇創設、年金増額や育児手当で報いる制度づくり。
- 子育てに伴う消費の地域社会への還元(子育て教育給付)を導入。
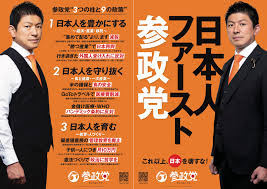
【まとめ】
少子化対策は、単なる支援制度の整備だけでなく、「価値観の転換」「経済的安定」「制度の包括的整備」が三位一体となって初めて効果を発揮します。
社会全体で出産・子育てを支え、未来の日本を創る土台をしっかり築くことが重要です。
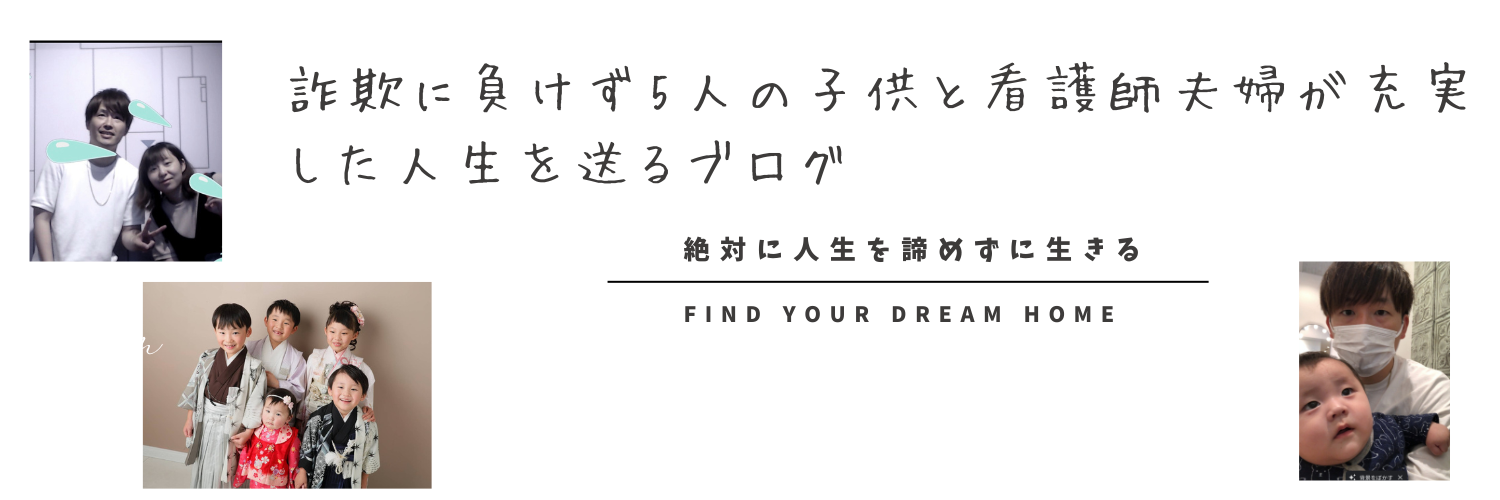
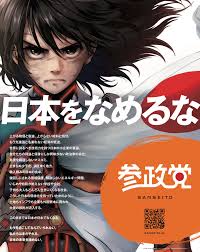
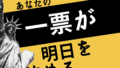

コメント